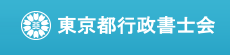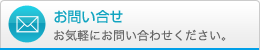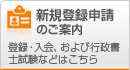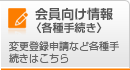4 一般貨物自動車運送事業
基礎知識
-
一般貨物自動車運送事業のうち、 つぎのものがあります。
(1)特別積合わせ貨物運送
一般貨物自動車運送事業として運送のうち、 営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分けをおこない、 集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、 運送された貨物の配達に必要な仕分けをおこなうものであって、 これらの事業場の間を定期的(1日1便以上)行うものいう。
(2)貨物自動車利用運送
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする運送をいう。
許可基準
- 事業計画が過労運転防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
- その事業の遂行上適切計画を有するものであること。
- 事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
基準の内容
1. 営業所
- 使用権限を有するものであること。
- 農地法及び建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
- 規模が適切であること。
2. 車両数
- 営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別)ごとに5両以上とする。
- 計画する事業用自動車にけん引車、 被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、 けん引車+被けん引車を1両と算定する。
- 霊柩運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょう(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの)の地域における事業については、 1.に拘束されないものであること。
3. 事業用自動車
- 事業用自動車の大きさ、構造等が運送する貨物に適切なものであること。
- 使用権限を有することの裏づけがあること。(自己所有、リース、これから購入など)
4. 車庫
- 原則として営業所に併設するものであること。 ただし、 併設できない場合は平成3年6月25日運輸省告示第340号(地域によるが、10km、20km以内)に適合するものであること。
- 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、 かつ、 計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
- 使用権限を有することの裏付けがあること。
- 農地法(昭和27年法律第229号)、 都市計画法(昭和43年法律第100号)等関係法令に抵触しないものであること。
- 前面道路については、 原則として道路幅員証明書により、 車両制限令に適合するものであること。・・・・・国道に面している場合は不要である。
5. 休憩・睡眠施設
- 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
- 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5m²以上の広さを有すること。
- 原則として、 営業又は車庫に併設するものであること。 ただし、 営業所に併設されていない場合であって、 車庫に休憩・ 睡眠施設するときは、 当該休憩・ 睡眠施設の所在地と休憩・ 睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10km(東京都特別区、 神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては、 20km)を超えないものであること。
- 使用権限を有することの裏づけがあること。
- 農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、 建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触しないものであること。
6. 運行管理体制
事業の適正な運営を確保するために、次の各号に掲げる管理体制を整えていること。
- 事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。
- 選任を義務づけられている員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
- 勤務割り及び乗務割が、平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。
- 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
- 車庫が営業所に併設できない場合には、 車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、 点呼等が確実に実施される体制が確立していること。
- 事故防止についての教育及び指導体制を整え、 かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年12月20日運輸省令第104号)に基づく報告の体制について整備されていること。
- 危険品の輸送を行う者にあっては、 消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令に定める取扱い資格者が確保されているものであること。
7. 資金計画
- 所要資金の見積もりが適切なものであり、 かつ、資金調達について十分な裏づけがあること。
- 自己資金が次に掲げるものの合算額の2分の1に相当する金額以上であること。
- 車両費・・・・取得価格(割賦未払金及び自動車取得税を含む)
- 建築費・・・・取得価格(新築の場合はm²標準単価×面積)
- 土地費・・・・取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)
- 保険料・・・・1.強制賠償保険料の1年分、2.賠償できる対人自動車保険1年分、3.危険物を取り扱う運送の場合は、 当該危険物に対応する賠償責任保険1年分
- 各種税・・・・自動車重量税、 自動車税、 登録免許税及び消費税の1年分
- 運転資金・・人件費(法定福利費及び厚生福利費を含む)、 燃料費、 油脂費、車両修繕費、 タイヤ、チューブ費のそれぞれ2ヶ月分に相当する金額
8. 法令遵守
- 貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
※ 許可申請時に法令試験の実施 - 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、 その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、 これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)が、 貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請目前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、 自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)でないこと。
9. 損害賠償能力
- 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償共済に加入する計画のほか、 一般自動車損害保険の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
- 石油類、 化成品類又は高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、 1.号に適合するほか当該輸送に対する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。
10. 許可に付する条件等
- 2.(3)に該当する事業については、 車両数について特例を認められ、 許可に際して当該事業に限定するなどの条件を付するものとする。
- 許可に際しては、許可日から1年以内に事業開始することの条件を付するものとする。
11. 特別積合せ貨物運送をする場合
省略します。
12. 貨物自動車利用運送事業を経営しょうとする場合
貨物自動車利用運送をする一般貨物自動車運送事業の許可申請に対する審査は、 上記の1から10迄の各項に加え、 次の各号についても審査するものとする。
- 貨物自動車利用運送に係る営業所については、1(1)から(3)によること。
- 業務の範囲については、 「一般事業」又は「宅配便事業」の別とする。
- 保管体制を必要とする場合は、 保管施設を保有していること。
行政書士に依頼するメリット
-
事業者の皆さんは運送実務や車両に関してはエキスパートですが、手続きや法律については必ずしも明るいとは限りません。行政書士は、法の要求事項とその保護法益を十分に理解し、許可取得希望者にアドバイスしながら正確に書類を作成いたします。また一般の方が手続を進める場合には行政庁に複数回足を運ばなければならないところを代理し、速やかに手続を完了することができます。
-
申請用関係書類の審査→申請書作成→運輸支局窓口申請書提出→法令試験の実施(合格)→運輸局書類審査→許可